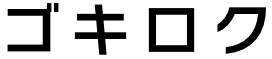命の重ね書き――『ガン患者の文通』を通じて考える生き方の選択
京都の風景と文通の始まり
最近、京都を訪れる機会がありました。古い街並みを歩きながら、ふと心に引っかかったのが、宮野真生子さんと磯野真穂さんの文通記録でした。この二人の文通は、京都の哲学者である宮野さんが乳ガンを患い、再発してしまったことから始まります。彼女がどんな思いで手紙を書いたのか、私は文通を通じてその一端に触れることができました。
京都の街を歩いていると、石畳の音がやけに心に響くんです。そんな風景の中で、宮野さんが磯野さんに初めて声をかけた場面を想像すると、なんだかとてもリアルに感じられました。宮野さんの「今すりゃええやんか」という言葉には、彼女の背負った現実と、そこに抗おうとする強い意志を感じました。
ガン患者の選択
ガンと診断されたとき、人はどのように生きるべきか。宮野さんが直面した選択は、他人事ではありません。私自身、もし同じ状況に置かれたら、と考えることがあります。「ホスピスを探してほしい」と医師に言われたとき、普通ならば恐れや不安が先に立つでしょう。でも宮野さんは「今、やりたいことをやろう」と思ったそうです。その強さに、私は胸を打たれました。
代替医療の話も、心に刺さるものでした。エビデンスがある標準治療を選ぶべきだとわかっていても、治るかもしれないという希望にすがりたくなる。宮野さんの文通相手、磯野さんが「選ぶの大変、決めるの疲れる」と言ったことに、どれほどの重みがあるのか、考えさせられました。
生きることと死ぬこと
この本を読んでいるとき、私は父が亡くなったときのことを思い出しました。父はガンではなかったものの、長い闘病生活の末に亡くなったのです。その時、私は「もっと父とあれこれ話しておけばよかった」と何度も思いました。宮野さんの言葉を借りるなら、「自分の人生を生きる」ということが、どれほど大切かを痛感しました。
宮野さんの「書くネタにしてやる」という言葉には、彼女の人生への前向きさ、そしてユーモアさえ感じました。悲しみに沈むのではなく、前を向いて生きる。その姿勢は、私にとって一つの指針となりました。
文通が教えてくれたこと
文通は、手紙という形でありながら、時に人と人を深く繋ぎます。宮野さんと磯野さんの文通も、単なる情報交換ではなく、互いの生き様や思いを通わせるものでした。それは、私たちが自分自身と向き合うための手助けにもなります。
宮野さんと磯野さんの文通を通じて、私は「どう生きるか」を考え直しました。ガンという命の危機に立たされながらも、彼女たちは自分の足でしっかりと立っていました。彼女たちの言葉は、今も私の心に残り続けています。
この本を読み終えた後、私は改めて自分の人生を見つめ直しました。宮野さんの生き方に勇気をもらい、磯野さんの言葉に心が癒されました。彼女たちの文通は、私にとって大切な人生の一部となりました。
読後、私はふと、京都の風景を思い浮かべていました。あの街の静けさと、宮野さんたちの言葉が、心の中で柔らかく重なり合い、何とも言えない安らぎを感じました。彼女たちの文通を通じて、私も少しだけ強くなれた気がします。