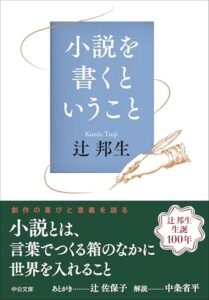辻邦生『小説を書くということ』が教えてくれた、書くことの意味と人生の普遍性
最近、辻邦生の『小説を書くということ』を手に取ってみました。この本に出会ったきっかけは、友人から「お前みたいな深く考えすぎるタイプにはぴったりかも」と言われたことでした。確かに、理系出身の僕にとって、物事を論理的に考えることは日常茶飯事。でも、そんな僕だからこそ、この本に出会えて良かったのかもしれません。
小説を書くということ、それは自身の世界の再構築
辻邦生は、ただ小説を書く技術を語るだけでなく、その根底にあるべき考え方を提示してくれます。彼の言葉を通じて感じたのは、小説を書くという行為が、単なる物語の創作に留まらず、自分だけの世界を再構築する試みだということでした。辻はこう語ります。「ぼくが死んでしまったら、この世界は消えてしまう」。この言葉に、僕はハッとさせられました。
普段、何気なく見ている景色や感じている空気、それが自分だけのものであり、誰とも共有できないものだとしたら、それを言葉にすることがどれほど大切なことか。僕の中で、小説を書くことは、自分の世界を未来に繋げる手段だという思いが芽生えました。
パルテノン神殿とポン・デ・ザール、二つの啓示
辻がギリシャのパルテノン神殿を訪れた際に得た「芸術の目的は、日常の混沌を乗り越え、秩序を作り上げること」という啓示。これが彼の創作に対する考え方の根底にあるといいます。僕も、大学時代に訪れた福岡の太宰府天満宮で感じたことを思い出しました。あの静謐な雰囲気の中で、日常の喧騒を忘れ、一つの秩序を感じた瞬間がありました。
また、パリのポン・デ・ザールで彼が理解したという「生の道理」。これについて辻は、世界にはすべて「ぼくの」という所有形容詞が付されていると話します。自分の視点でしか見られない世界、これは僕にとっても大きな発見でした。日々の生活の中で、どれだけのことを見逃しているのか。そして、それを書き留めることがどれほど重要か。
書くことの健康と精神の維持
辻は、どんなに退廃的な物語を書いたとしても、創作に向き合う精神は健康でなければならない、と力説しています。これを読んで思い出したのが、以前読んだノンフィクション作品で感じた作者の静かな怒りです。理不尽な社会の中で、どうやって自分の精神を保つか。それは、日々の生活の中で「生命のシンボル」を見つけることだと彼は言います。
僕自身も、日常の中で小さな喜びや感動を見つけ、それを大切にしています。それが、本を読むことだったり、何気ない会話の中にあったり。辻の言う「一回こっきりの人生を生きる覚悟」がここに繋がるのだと思います。
イマージュとしての小説
辻が小説を書く上で強調するのは、出来事を単なる事実の羅列にしないこと。全体を一つの「イマージュ」として捉えることが重要だと説きます。この考え方に触れたとき、僕は自分の日々の過ごし方を少し変えるべきだと感じました。目の前の出来事をただの情報として見るのではなく、その背後にある感情や雰囲気を感じ取ること。それを言葉にすることで、初めて自分の世界を他者に伝えることができるのだと。
この本を読んでから、僕は日記を書くようになりました。何気ない日常の中で感じたことを、言葉にして残す。それが、もしかしたら未来の自分にとって、かけがえのない財産になるのではないかと思ったのです。
辻邦生の『小説を書くということ』は、小説家を目指す人だけでなく、生きることに迷いや不安を感じている人にもぜひ読んでほしい一冊です。派手な表現や劇的な展開はありませんが、心の奥深くにじわじわと染み込んでくる力を持っています。最後まで読み終えると、静かに泣けるような、そんな感動が待っています。