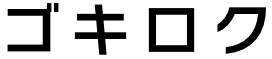孤独と向き合う言葉たち『名もなき孤児たちの墓』中原昌也に感じたもの
私は普段、京都の大学で哲学を学んでいる学生です。そんな私が、どうしても心を動かされた本があります。それが中原昌也さんの『名もなき孤児たちの墓』です。この本を手に取った時、何かしらの啓示を受ける予感がありました。表紙の質感やそのタイトルから、ただならぬものを感じたのです。
言葉の孤児たちとの出会い
中原昌也という作家は、私にとって「言葉の魔術師」とでも言うべき存在です。彼の書く物語は、時に理解を拒み、時に心の奥底に問いを投げかけてきます。『名もなき孤児たちの墓』に収録されている短編「点滅……」はまさにその象徴です。読んでいる途中で、何度か立ち止まらざるを得ませんでした。
最初に読んだとき、私は「これは一体何を言わんとしているのか」と戸惑い、少しずつページをめくるのが怖くなりました。けれど、その一方で、何かを逃してしまうような気がして、読み進めることを止められなかったのです。もしかしたら、私がこの本から得たものは、はっきりとした「答え」ではなく、「問い」そのものだったのかもしれません。
日常の中の異化
この作品の中で語られるのは、日常から少しずつ剥ぎ取られる「当たり前」の感覚です。デパートの屋上で立ち尽くす〈俺〉や、急死を告げられた田辺次郎の話には、どこか現実味が薄く、それでいてこちらの心に強く残る違和感があります。これが中原さんの言う「異化」という手法なのかもしれません。
私が日常の中で感じる小さな違和感や戸惑いを、そのまま物語として形にしてくれるように感じました。私たちは時に、何が「本物」なのかを見失うことがあります。中原さんの作品は、そんな私たちを静かに問い詰めるのです。「本当に見えているものは何なのか?」と。
問いかける小説の意味
中原さんの作品を読んでいると、どうしても考えずにはいられない問いがあります。それは「小説とは何のために存在するのか?」ということです。私は普段、小説を楽しむことも多いですが、こうした作品に出会うと、ただ楽しむだけではいけないような気がしてきます。
中原さんがこの作品で伝えようとしているのは、「誰の欲望も満たすことの絶対にない小説」の価値ではないでしょうか。それは、私たちが普段求める快楽や安心感とは違う、もっと深い意味を持つものです。私はこの作品を通して、言葉が持つ力を再認識しました。言葉は時に、私たちを救うこともあれば、迷わせることもある。その両面性こそが、言葉の力であり、魅力なのだと思います。
読み終えて感じたこと
『名もなき孤児たちの墓』を読み終えた時、私は強い孤独感と同時に、奇妙な安堵感を覚えました。この本は、私にとっての「言葉の孤児たち」との出会いでした。それは、未完成で不完全な、自分自身の心の中にあるものと向き合う時間でもありました。
この本を手に取る読者は、もしかしたら私と同じように、何かしらの問いを抱えることになるでしょう。でも、それでいいのだと思います。問いかけることこそが、私たちが生きている証であり、答えを求める旅の始まりなのです。中原昌也さんの作品に触れることで、その旅に出る勇気をもらった気がします。結論は出せないけれど、これが今の私の読み方です。