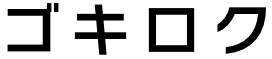「熟柿」を読む――愛を求め続けたひとりの母の物語
こんにちは。今日は佐藤正午さんの『熟柿』について、私が感じたことをちょっとお話しさせてください。この本を手に取ったのは、タイトルに惹かれたからでした。「熟柿」って、完熟した柿のことですよね。甘くて、柔らかくて、でもどうしようもないくらいに儚い。そんな印象を受けて、ページをめくり始めました。
心に残った「わたし」の姿
物語の中心には「わたし」という女性がいます。彼女の名前は最後まで明かされないのですが、そのことがかえって、彼女の孤独や葛藤を強調しているように感じました。妊娠中にひき逃げ事故を起こしてしまった彼女は、獄中で出産し、子どもを抱くこともできずに夫に引き取られてしまいます。
この設定だけでもう胸が締め付けられるようで、なんだかすぐにでも彼女に肩を貸してあげたくなるような気持ちになりました。私自身はまだ学生で、子どももいないけれど、「母親になる」ということの重さや大変さを考えさせられました。彼女がずっと子どもに会いたいと願いながらも、隠れて生きざるを得ない状況が、まるで逃げ場のない迷宮に閉じ込められたような、そんな絶望感を感じさせます。
土地を転々とする「わたし」の旅
この小説の中で「わたし」は様々な土地を転々とします。山梨県の石和温泉、岐阜県の大垣市、大阪市、そして福岡市。それぞれの地で彼女は生きるために、そして子どものために働き続けます。私はその描写を読んで、なんだかちょっとしたロードムービーを観ているような気持ちになりました。
土地を変え、環境を変え、それでもどこか変わらない「わたし」の思い。それは、私の中にもある「どこに行っても変わらないもの」の存在を思い起こさせました。例えば、私が京都で学んでいても、どこか違う町に行っても、心の中にある「本を読むことが大好き」という気持ちが変わらないように。
静かに差し込む希望の光
この小説には、厳しい現実に打ちひしがれながらも、ほのかに希望の光が差し込んでいます。特に「わたし」が子どもを受取人にした生命保険に入る場面は、彼女の愛が形を持って現れた瞬間で、思わず目頭が熱くなりました。彼女は直接会うことができなくても、確かに自分の存在を子どもに伝えようとしているのです。
私がこの本を読み終えたとき、ふと、子どものころに書き溜めた日記のことを思い出しました。誰にも見せるつもりがないのに、ただ自分のために書いていたあの時間。もしかしたら、「わたし」が書き続けた手紙も、そんな風に彼女自身を支えるためのものだったのかもしれません。
読み終えて、感じたこと
『熟柿』を読み終えた今、この物語が私にとってどんな意味を持っているのか、まだ完全には言葉にできません。でも、たぶんそれで良いのだと思います。この小説は、正しさや答えを求めるのではなく、ただ「わたし」というひとりの女性の人生を追いかけ、彼女の心に寄り添うことを大切にしているように感じました。
「……たぶん、そういうことなんだと思います」。私がこの本を通じて感じたものは、今はこうして曖昧な言葉でしか表現できないけれど、やがてどこかで、私の人生の中で意味を持ってくるのかもしれません。そんな期待を抱きつつ、本を閉じました。
興味があれば、ぜひあなたもこの『熟柿』を手に取ってみてください。そして「わたし」の旅を一緒に辿ってみてください。きっと何か心に残るものがあるはずです。