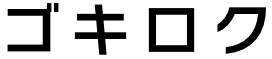「今・此処」の不思議を探し求める旅 ― アン・タイラー『あのころ、私たちはおとなだった』を読んで
アン・タイラーの『あのころ、私たちはおとなだった』を手にしたとき、私は不思議な感覚に包まれました。この本を読んでいる間、まるで心の中に小さな窓が開いたような気がしたんです。その窓から見える景色は、私自身の人生とどこか重なるものでした。タイラーは、まるで魔法のように、日々の中のささやかな瞬間を切り取って、私たちに見せてくれます。彼女の物語の中で、その瞬間は鮮やかに輝き、私たちの心に深く刻まれるのです。
人生のターニングポイントを見つめる
主人公のレベッカの姿には、多くの人が共感を覚えるのではないでしょうか。彼女は貸し宴会場「オープン・アームズ」を経営し、家族の中で奮闘する日々を送っています。そんな中でふと、「私はどこへ行ったんだろう?」と自分を見失いそうになる瞬間があります。私自身も、ふとした瞬間にこんな問いを抱くことがあります。大学で哲学を学びながらも、その答えはなかなか見つかりません。タイラーの描くレベッカの姿は、そんな私の心の奥深くにある不安や迷いを、そっと覗き込んでくれるようでした。
人生の分岐点は、いつだって突然訪れます。それはレベッカが19歳の時にウィルとの別れを選んだ瞬間だったり、あるいは夫ジョーとの出会いだったり。レベッカが感じた「ある瞬間にすべてのことの芽が含まれている」という感慨は、どこか哲学的でありながら、日常の中に潜む真実を映し出しています。私たちの日々も、何気ない瞬間の連続でできているのだと改めて感じさせられました。
過去と現在の交差点で
物語が進む中で、レベッカは過去の恋人ウィルと再会し、彼女自身の「そうなっていたかもしれない人生」を夢想します。これがまた興味深い展開で、私も思わず自分の過去を振り返ってしまいました。もしあの時違う選択をしていたら、今の自分はどうなっていたのだろう?大学に進学せずに別の道を選んでいたら、どんな人生が待っていたのだろう?
ウィルとの再会シーンは、少し滑稽でありながらも心に残るものがあります。タイラーのユーモアは、現実の厳しさや切なさを和らげてくれるのです。思い出すのは、私が久しぶりに昔の友人と再会したときのこと。彼らの変わった姿に驚きつつ、でもどこか懐かしさがこみ上げてきたあの瞬間に、レベッカの気持ちがリンクしました。
今・此処を生きるということ
最終的にレベッカが選択するのは、「今・此処」を生きることです。彼女はかつての自分を手放すことなく、しかし新たな自分を受け入れる道を選びます。それは、私たちが日常で直面する選択と似ているように感じました。何度も立ち止まり、迷い、また歩き出す。そんな繰り返しが、私たちの人生なのかもしれません。
アン・タイラーの物語は、どこか優しく、そして力強いメッセージを私たちに届けてくれます。レベッカの選択は、私たちが自分自身に問いかけている「これでいいのか?」という不安に対する小さな答えのように感じました。タイラーの作品は、静かなけれど確かな希望をもたらしてくれるものです。
読後、私はふと窓の外を眺めました。京都の街並みがいつもと変わらず広がっているのに、不思議と心は軽くなっていました。アン・タイラーの『あのころ、私たちはおとなだった』は、そんな「今・此処」の不思議を垣間見せてくれる一冊です。結論は出せないけれど、これが今の私の読み方です。